ジャージーボーイズ

監督:クリント・イーストウッド
出演:ジョン・ロイド・ヤング、エリック・バーゲン、マイケル・ロメンダ、ヴィンセント・ピアッツァ他
2014年 アメリカ映画
“栄光と挫折”
クリント・イーストウッドがブロードウェイミュージカルを映画化。
60年代のアメリカの音楽シーンをぎゅっと詰め込んだ作品です。
フォーシーズンズは今でも耳なじみのあるヒット曲を出している伝説のグループ・
犯罪も多く、ドラッグも蔓延していたニュージャージーの貧しい町から、歌を愛しスターになっていく4人のメンバーを描いている。
少しうまく行くと、裏切りや挫折、別居、家族の死と、人生のアップダウンがこれでもか?と繰り返されていく。
アーチストとしての栄光と、人生の苦悩。
スターを見ると、テレビやステージではいつも笑顔なので、「あんな人生うらやましいな」と思っている人も多いと思うが
プライベートでは多くの苦悩や挫折を抱えているものである。
その様子を見せずに、人前に立つからこそ、スターはスターでいられるのかもしれない。
スターだけでなく、自分の身近にいる人でも、笑顔の裏には苦悩を隠している人も多いであろう。
人気者の真の姿を映し出しているこの作品は、人間の強さと弱さの両方を教えてくれる。
ヒットソングと共に、「栄光と挫折」の両面からスターの生きざまを感じさせてくれる興味深い1本です。
グローバル・メタル

監督:スコット・マクフェイデン、サム・ダン
出演:アベッド、アハミド、アリ他
2007年 カナダ映画
“世界のメタル事情”
世界中のメタラーが絶賛した「メタル ヘッドバンガーズ・ジャーニー」の監督サム・ダンが
ヘヴィメタルのグローバル化について扱ったドキュメンタリー映画。
この作品の注目点は、アメリカやヨーロッパを一切扱わず、ブラジル・インド・中国・インドネシア・イスラエル・UAEそして日本という
メタル発祥地でない国々を取り上げているところにある。
日本以外の国はヘヴィメタルの発展は政治や社会情勢に大きく関与している。
ブラジルは独裁政治からの解放、インドネシアは貧富の格差、中国は共産主義と儒教思想から若者達が自由を求めたこと、
インドはカースト制への反骨精神、イスラエルは戦争へのいらだちなど…。
日本だけは独特な発展を遂げている。社会への反感などでなく、「ストレスの発散」や「音楽としての追求」
ヘヴィメタルに「反骨精神」を求めているのでなく「楽しみ」を求めている。
日本で開催されるラウドパークでは男女関係なくメタルTシャツを着て笑顔で一緒に盛り上がっている。
その他の国のライブを見ると男だらけだ。
もちろん、イスラム教の国などは女性が男性と一緒にライブを見るということですら難しいかもしれないが、
国によっては危険思想の音楽として地下(アンダーグラウンド)でやるしか無い国もある。
血気あふれる男達が集まって自由や正義の為にメタルライブで自分のアイデンティティを探しているという感じだろうか?
僕自身は日本という国に生まれ、日本人としてヘヴィメタルに関われている自分を幸せに思う。
他国の人から見ると変な人種に思われるかもしれないが、「音」を「楽しむ」という音楽という言葉がある日本は素晴らしい。
インターネットによりヘヴィメタルはもっとグローバル化するだろう。
新しい時代はどんな時代になるのか?
余談だが、この映画でSEX MACHINEGUNSの日本武道館のライブが取り上げられている。
楽しそうなファンの笑顔。他国には無い日本のメタルだ。
アンヴィル!夢を諦めきれない男たち

監督:サーシャ・ガヴァシ
出演:スティーヴ・“リップス”・クドロー、ロブ・ライナー、ラーズ・ウルリッヒ他
2009年 アメリカ映画
“メタルのリアルな世界”
日本でも有名なヘヴィメタルの大御所“ANVIL”のドキュメンタリー作品。
近年、幕張メッセのラウドパークですごい集客をしたし、ロックTシャツを売っている店では
必ずANVILのTシャツは見るので、今だにカナダではロックスターとして輝かしい生活を送っていると思っていた。
オリジナルメンバーは。ボーカルギターのリップスと、ドラムのロブ。
この2人が、給食の配送や解体屋をやっているなど、予想だにしなかった。
ヨーロッパツアーで一円にもならないなんてイメージすら出来ない。
大きなフェスティバルの話しか聞かないので、すごく売れているイメージしかないのだ。
肉体労働で食いつなぎ、インディーズで手売りをしているバンドが、世界中にファンを持っているなんて…。
ロブとリップスの絆、そして50になっても追い続ける夢。
2人の激しすぎるパーソナリティが彼らを伝説にしているのであろう。
1つのことをここまで追求している彼らは、悩み、壁にぶつかっているが、魂も重金属=メタルである。
真のメタルマンなのだ。
しかし、王道とは言えないヘヴィメタルのリアルな世界を見た気がした。
もっとポップスの要素を取り入れたら、メジャーだって契約する可能性もあるだろう。
しかし、ANVIL流メタルを追求し続ける。
「夢は若者が追うもの」的思考の人も多いが、いくつになっても夢を追う男の姿は笑えるし泣けてしまう。
ヘヴィメタルは、ただの音楽ではない。生き方なのだ。
BECK

監督:堤幸彦
出演:水嶋ヒロ、佐藤健、桐谷健太、忽那汐里他
2010年 日本映画
“バンドは運命の集団”
ハロルド作石の人気バンド漫画「BECK」を実写化したこの作品は、水嶋ヒロや向井理、佐藤健など
イケメン達や人気俳優がたくさん出演しているので、アイドルムービー的扱いで見た人も多いかもしれないが
バンドとは何か?を教えてくれる作品である。
普通のバンド映画は、全員不良とか、エネルギーが有り余って同じような人間同士が集まっていることが多い。
しかし、BECKというバンドは、メンバーのキャラクターがバラバラである。
気弱で無気力の子もいれば、ケンカっ早いイケイケもいる。
クールな男もいれば、普通の青年もいる。
きっと普通の生活では一緒にいないであろう5人が、音楽という1つのキーワードで結ばれていく。
共に喜び、そして苦しむことで、全員が1つになっていく。
「運命」はただの奇跡でなく、同じ時間の流れを共有することで1つになっていく。
その時間を一緒に過ごすことそのものが「運命」なのかもしれない。
ロックフェスのシーンで、アンダーグラウンドHIPHOPの帝王「ZINGI」が出てきたり、
音楽的に楽しめるところもたくさんある作品である。
自分とカラーが違う人だから認めないのではなく、自分が持っていないものを持っている人だと思い認めることこそ
世界が広がることなんだと教えてくれる作品です。
自分の新しい世界を見つけたいのに何も出来ない人は、この作品を見て背中を押してもらうと良いでしょう。
クレイジー・ハート

監督:スコット・クーパー
出演:ジェフ・ブリッジス、マギー・ギレンホール、ロバート・デュヴァル他
2009年 アメリカ映画
“変われるもの、変われないもの”
数十年前ヒット曲を出し有名になったミュージシャン“バッド”。
その名声だけで、曲も作らず酒におぼれ、田舎の営業を回り、日々生きている老いぼれアーチスト。
本当は才能があるのに、朝から飲んでダラダラした生活を送っていた。
ステージもまともに立てないくらい飲んだくれていた男も、
1人の女性新聞記者との出会いで、止まっていた時計の針が動き出す。
自分の弟子がヒット曲を出し、逆恨みの対象にしていたが、
生活する金も無くなってきたので、しぶしぶ前座で出演する。
弟子は単に自分を育ててくれたバッドへの感謝と、
もう一度やり直すチャンスをお礼として渡したかったのだが、
その気持ちをバッドはなかなか受け入れられない。
年をとって過去のことを自慢するのは楽だが、未来に向け自分を変えられる力は無かった。
年齢を重ねると生活や考え方を変えることは、若い頃に比べて困難かもしれない。
上手くいっていたり、満足している人間には必要ないかもしれないが、
こんな人生の終着点を求めていたわけではないのに…という人間は、
苦しくても変わらなくてはならない。
老いていく1人のミュージシャンを通して、悩みながら変わっていくことの大切さを描いている。
エンディングは、青春映画のように全てがハッピーエンドではないかもしれないが
長年やってしまったこと、何より彼に未来が出来たことを考えると
ハッピーエンドと言ってよいであろう。
長くやってしまったことは、そう簡単には取り戻せない。
だからこそ若い人にこの作品を見てもらい、早い段階で人生の手術をしてほしい。
人生も早期発見が大切なのかもと思わされる映画です。
「変われるもの」「変われないもの」両方を抱え生きていくのが人間なのかもしれません。
エア☆ドラム!世界イチせつないロックンローラー

監督:アリ・ゴールド
出演:アリ・ゴールド、マイケル・マッキーン、ジェーン・リンチ他
2008年 アメリカ映画
“オタクのロック魂 ここに在り”
労働者として貧しい中でも“ロック”を愛する1人のエアドラマーを描いた作品
“エア☆ドラム!世界イチせつないロックンローラー”
エアギターは聞いたことあるけど…という人は多いと思うが、そのドラム版である。
きっとロックオタクであろう監督(主演もこなしている)の“妄想の世界”が綴られている暴走作品。
しかし、ここまで暴走してくれると、自然と笑いが出てくる。
貧しくてドラムを買えない1人の青年。対抗するは金持ちで父の働く工場の社長息子。
この対決構造。
何かに取り組んでいる男を好きになる傷害を持った女性との恋。
しかし、この恋にも壁が多くある。
ストライキをして体制に対抗する父。勇気付ける為、ダメな自分の真剣な姿を見せる主人公。
そして友情と勝利。
とにかくどこにでもありそうなテーマをやたらと集めてきて、良いお話にしようとしているのだが
“エアドラム”という滑稽なもので熱くやっているので、ストレートに感動できずついつい笑ってしまう。
まるでアルヤンコビックのPVを見ているようだ。
しかし、90分もやられ続けると、笑いの中に、主人公を応援してしまっている自分に気付き
はっとさせられる。
表現が重くないので、後から気付くと、“Rock”の持つ前向きなスピリッツを自然に受け入れてしまうだろう。
オタクの“パワー”を通して、ロックのスピリッツを教えられる。なんとも不思議な映画です。
こんなアプローチもありかも?
ロック好きの人が見ると笑えるところは山のようにあります。
僕らのワンダフルデイズ

監督:星田良子
出演:竹中直人、宅麻伸、斉藤暁他
2009年 日本映画
“音と記憶”
自分が癌で余命が少ないと思い込み、高校の頃のバンドを再結成し、
最期は輝いた人生だったと思いたいと思った男と元バンド仲間のオヤジ達を描いた“僕らのワンダフルデイズ”
この作品の中ですごく印象的だった言葉は
“死ぬ前最後まで残っているものは音の記憶”“音楽で残しておきたい”という言葉。
竹中直人演じるノリだけの男が、死を自分に感じた時、悩みぬいて感じたことが“音”への執着だった。
皆それぞれ仕事をして生活があって、決して楽な人生ではない。
しかし、そんな中、笑って楽しんで音を創り上げていくことで“和”が出来、“輪”になっていく。
バンド=結ぶ。
バンドはずっと会っていなかった人間関係も結んでいく。
音楽の持つ力は目には見えない。音は心を結んでいく。
オヤジになっても、音楽で結ばれていく人達は何故か微笑ましい。
普段は情けない父の姿も格好よく見えたりする。
本当に好きなことをやっている姿を子供達に見せることで、子供達は喜び、
家族の絆を深くすることも出来る。
この作品は是非家族で見て欲しいバンド映画です。
バンガー・シスターズ

監督::ボブ・ドルマン
出演:ゴールディ・ホーン、スーザン・サランドン、ジェフリー・ラッシュ他
2002年 アメリカ映画
“逆の視点”
60年代グルーピーとして名を馳せていた2人の女性の20年後を描いた“バンガー・シスターズ”
グルーピーとは、今で言えばミュージシャンの追っかけ、ファンのことだが、
時にはミュージシャンに抱かれたり、近い存在になり、ファンの頂点みたいなものと言えば伝わるだろうか?
この映画の面白いところは、音楽映画で「アーチストの数年後」というテーマの作品はたくさんあるのだが、
「ファンの20年後」という逆の目線で描かれた作品であるというところ。
ファンにだって人生はあるのだから、十分題材として成立するのだろうが、この“逆の視点”には正直びっくりした。
ストーリーは、グルーピー時代の自由な生き方を貫いている1人の女性と、
グルーピー時代を捨て社会に合わせ生きるもう1人の女性。
当時共に、グルーピーとして名を轟かせていた2人の人生は180度異なる方向を向いていた。
20年ぶりに2人は再会するが、お互いの生き方を認めることが出来ない。
しかし、時間を共有することで、2人は再び近づいていく。
この作品を通して感じることは、“自分らしさ”を持って人生を歩んでいくことの重要性である。
自分の過去は捨てることは出来ない。
年齢を重ねて今の生き方と違う過去があったとしても隠すのではなく、
“経験”や“過程”として、今の自分を作ったものなのだから大切にした方が良い。
“自分の生きてきた道”それは自分しかもてない宝物だと教えてくれる作品です。
ストーンズ・イン・エグザイル

監督:スティーヴン・キジャック
出演:ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ビル・ワイマン他
2010年7月12日〜 渋谷アップリンク・ファクトリー他全国順次公開
アメリカ・イギリス合作映画
“転機という通過点”
60歳を過ぎても世界中をツアーし、常にトップを走り続けるグレートロックグループ
“ローリングストーンズ”
そんなストーンズの70年代初頭の様子をフィルムや写真で綴ったドキュメンタリー作品である。
イギリスを拠点にしていたストーンズのメンバーは、税金があまりに高いので、
生活や制作のベースをフランスに移してしまう。
フランスに住んだメンバーにとって、南仏の楽園は、音楽制作という環境が整っていなく
ライブレコーディングなどで使う録音車を、キースの家の敷地に停め、
地下室をレコーディングスタジオにし、録音し始めるのである。
そこはメンバーだけでなく、家族や、共にサウンドを作るミュージシャン達のアジトのようになっていった。
公開映画なので、ドラッグやセックスなど本当に危ないものはフィルミングされていないが、
写真やフィルムの断片から、危ないにおいは少し感じられる。
メンバー交代はあったものの、長年続き、トップを走り続けるバンド“ローリングストーンズ”には、
いくつかの転機があっただろう。
その1つを、この作品で見ることが出来る。
自分達で環境を作り、世間の非難も聞こえただろうが、自分達の生活を貫いていく。
バンドという個性の集合体は、転機という通過点を通ることで、アルバムやツアーという子供達を産み落とす。
世界中に羽ばたいていく。
共に大きな戦いをした後、グループやチームは、ビジョンが明確になるものである。
偉大なストーンズの歴史の中で、この転機があったからこそ、今のストーンズがあるのだと
思わされる作品である。
転機を乗り越えた時、それは、ただの通過点となる。
ROCKER 40歳のロック☆デビュー

監督:ピーター・カッタネオ
出演:レイン・ウィルソン、ジョシュ・ギャッド、テディ・ガイガー他
2008年 アメリカ映画
“過去との向き合い方”
ドラムをメンバーチェンジすることを条件にデビューを約束してもらったバンド。
ドラマーは、メンバーにあっさり捨てられ、そのバンドは後にロックスターとしての座を獲得した。
ビートルズのピート・ベストのようだ。ピート・ベストもビートルズデビュー直前に解雇された。
主人公のフィッシュもヘビメタバンド“ヴェスヴィオス”の中心的メンバーであるのに、
芸能界のパワーを使われ、解雇されてしまう。
“ヴェスヴィオス”はその後スターになる。
ナイトレンジャーやクワイエットライオット、ガンズアンドローゼスをMIXしたようなバンドが
今でもうけているという設定がちょっと笑えるが…。
フィッシュはドラムやバンドがトラウマになる。
しかし、デブでモテない甥が「プロム」でバンドをやりたいという夢を叶えるため
ドラムを叩くことになる。
元々ロックの血が流れていたフィッシュは、再びバンドをやるという道を選ぶ。
誰の力も借りず、YouTubeだけで一躍有名になった中年と高卒してすぐのバンド“A.D.D.”は
レコードメーカーに目をつけられ、デビューする。
やがて、ビックチャンスがやってきた。しかし、それは“ヴェスヴィオス”の前座だった。
過去、自分を捨てたバンドの前座なんて、フィッシュにとっては最もやりたくない仕事だった。
2万人の前でのライブのチャンスを捨てようとするフィッシュに、20歳近くの若い3人は反対。
フィッシュはバンドを辞め、サラリーマンを始めた。
再び同じ境遇を味わったのである。
しかし、3人の若者達はフィッシュをバンドに戻るように訴える。
過去を捨て、夢に向かう大切さを子供達から教わるのだ。
バンドをやっていると、家族のように一体化する。
だからこそ、バンドの解雇は、家族から捨てられるようなものだろう。
“同じ苦しみを味わいたくない”
“過去のトラウマ”にこだわっていては前に進めない。
バカで笑えるストーリーだけに、余計哀しさが伝わってくる。
しかも、ピート・ベストがカメオ出演しているのも皮肉たっぷりだ。
前を向いて歩き出したい人にオススメの1本です。
パイレーツ・ロック

監督:リチャード・カーティス
出演:フィリップ・シーモア・ホフマン、トム・スターリッジ、ビル・ナイ他
2009年 アメリカ映画
“Rock is never Die”
イギリスが、ビートルズやストーンズを低俗な音楽として批判していた頃、
船の上から海賊版ラジオ局として、ロック・ポップス専門局として自由にやっていた放送局と
政府の戦いを面白くストーリー化した作品“パイレーツ・ロック”
今となっては当たり前のサウンドとして、生活に根付いているロックも、
かつては低俗で卑猥な音楽とされていた。
アメリカですら、エルビスの腰の動きや歌詞を非難し、
子供達に悪影響を与える“悪の音楽”と言っていた時期もあった。
ストレートにリズムに乗せて、愛を唄ったロックンロール。
少し危なくて、踊れて、新しい風を運んできた当時のロックに、多くの人が熱狂した。
それは、政治でつぶすことも出来ない大きな力になっていく。
ともかく、ロック専門局にいるDJ達は、自由である。
この自由なスタイルもクラシックな大人達には、鼻についたのかもしれない。
この作品を見て思ったこと、それは「ロックは自由」ということである。
指揮者がいて縛られるのでなく、自分の思ったように生きることこそ、ロックなのである。
もちろん、それぞれが“自由”に生きているから、個性がぶつかることもある。
その個性をとことんぶつけきり、相手を認めれば、さらに絆が生まれていく。
恋愛、親子、プライド、スタイル、全てが個性と共に成長し、仲間を作っていく。
コメディ的な作品なのだが、そんなロックスピリッツが全編貫かれていて、
作品中、気持ちよいロックサウンドが流れ、楽しくロック魂に触れることが出来る。
“ロックは死なない”
Rock is never Die!!!
シド・アンド・ナンシー

監督:アレックス・コックス
出演:ゲイリー・オールドマン、クロエ・ウェッブ他
1986年 イギリス映画
“ドラッグの先にあるもの”
セックスピストルズのベーシスト“シドビシャス”と恋人ナンシーの破滅的人生を映画化した“シド・アンド・ナンシー”
イギリスの伝説のパンクバンドで、王室否定、パンク的未来否定、ファッション、暴れまくるステージング…
多くのパンクスタイルを見せ、後世に影響を与えたバンドである。
この作品の軸にあるのは、“ドラッグと愛”
本当の話の映画化なのだが、ドラッグの先にあるもの… それは崩壊である。
ドラッグの先に未来など無いのである。
“パンクと崩壊”は、紙一重なのかもしれないし、シドの生き方は、彼らにとって“リアル”に映ったかもしれない。
その破壊的な人生が、シドをスターにしたのかもしれないが、
それは孤独にさせられていくことでもあるだろう。
“ファッションパンク”という言葉もあるが、長く続けるには必要なことかもしれない。
今回“〜かもしれない”という言葉を多く使っていることは、自分自身も気づいている。
「リアル」の大切さや重要性は分かっているし、
人間が他人の超人的なアナーキーな生き方に魅せられることは理解するが、
その人生が後々素晴らしいと言い切れるかと考えると疑問が多いからである。
とにかく自分が言えることはドラッグの先には何も無いということだけである。
美談にしても、何の意味も無いのである。
この作品を否定しているわけではない。
この作品を冷静に多くの人に見てもらいたいだけである。
アナーキーに生きることの否定でなく、ドラッグの否定をしているだけである。
本当に気づいてほしい。
ドラッグの先にあるもの… それは自己崩壊。
ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト

監督:マーティン・スコセッシ
出演:ザ・ローリング・ストーンズ
2008年 アメリカ・イギリス映画
“ライブの魅力”
60歳を過ぎてなお、世界のトップアーチストとして君臨するローリング・ストーンズの
NYでのライブをマーティン・スコセッシが撮った作品“ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト”
スタジアムでなくホールに客を詰め込み、コンサートでなくライブの魅力がぎっしり詰まった1本です。
ドキュメンタリーというよりは、1日のライブを中心に、時々昔のテレビでのインタビューなどが入ってきたり、
コンサート直前のリハーサルや打ち合わせなどをピックアップした作品。
ライブは、バディ・ガイやクリスティーナ・アギレラなどがゲストに登場。
クリントン夫婦も客として見ていて、まさにスペシャルライブ。
ライブ感たっぷりな作品なので、昔、日本でよくやっていたフィルムコンサート気分で見ると
気持ち良く見れるだろう。
圧倒的なミック・ジャガーのステージング、
あいかわらず煙草をステージで吸いながら独自のスタイルでギターをかきならすキース、
シャープにロックしているロン・ウッド。
そんな個性をまとめ、ビートを作り出すドラムのチャーリー・ワッツ。
「これが60歳過ぎた男達のステージングか?」と思わず画面に言ってしまうくらい、
アクティブにお客を動かしていく。
ロックの持つパワーを感じさせられた。
さらに、アップが多く、表情をしっかり見ることが出来る。
楽しそうな顔、客をあおっている顔、やさしい顔…色々な顔が曲ごとに強烈に印象を残していく。
スタジアムでは感じられない、映像だからこそ表現出来るライブの面白さがこの作品にはあった。
自分もライブを撮影している人間として、すごく参考になる作品である。
こんな不良オヤジ達に世界が興奮するのも仕方が無い。
きっと1日のライブだけで、こんなに弾きつけることが出来る60代のバンドなんて、
世界中どこを探してもいないであろう。
少年メリケンサック

監督・脚本:宮藤官九郎
出演・宮崎あおい、木村祐一、佐藤浩市 他
2008年 日本映画
“日本初パンクミュージックコメディ”
監督・脚本が宮藤官九郎なので、笑いと音楽が軸になって舞台的な展開をしていく。
キャラクターが生き生きして、ロードムービー的要素もある。
監督本人が役者もバンドもやっているから、格好悪い表現が無いし、
ノリを知っていてあえて格好悪いものを入れて笑いにしているところなど、
2時間近い作品なのにあっという間に見れてしまう。
遠藤ミチロウや仲野茂など日本の本物のパンクロッカーや、ピエール瀧などのミュージシャンも数多く出演している。
途中アニメーションを使うなど、“ナチュラルボーンキラーズ”的、POPなのに危ないテイストを出している。
日本のPOPS、タイアップ主義の音楽シーンをバカにしながら否定しつつ暴れている感じは、
映画自体もPUNK精神を打ち出している。
PUNKは、体制側にいつも反発するものだ。
商業映画でそれをやっていることが面白い。
中年のパンクロッカーを、佐藤浩市、木村祐一が自然にこなしている。
大人なのにガツガツしている感じが、若い人がガツガツしているのに比べ、なんだか悲しみさえ感じてしまう。
田口トモロヲがさらにもの悲しさを深めている。
大人が“反発”したり、“暴れる”と、大人気ないと思われるかもしれないが、僕は熱く生きていく彼達に共感できる。
PUNKは音楽ではなく、生き方である。
PUNKな生き方をしている人間は、一生PUNKとして生きていける。表現方法は変わっていくかもしれないが…。
この映画は笑いながら、熱さを取り戻せる映画である。
自分自身をさびさせないで生きていくために、是非見てほしい1本である。
Aサインデイズ

監督:崔洋一
出演:中川安奈、石橋凌、広田玲央名 他
配給:大映
1989年 日本映画
“オキナワンロックが返還された日”
60年代後半の沖縄のバンドを通し、アメリカ占領下の沖縄の現実と若者達の姿を描いている作品“Aサインデイズ”
正直こんなすばらしいロック映画が日本にあったことに驚いた。
崔洋一監督のリアルな演出、そしてバンドの持つ独特な感じをきちっと描いている事は賞賛に値すると思う。
僕自身もこんなバンド映画を撮ってみたい。
ARBの石橋凌がかもし出す空気とバンドが持っている格好良い部分と格好悪い部分がしっかり融合されていて
ドキュメンタリー的なリアリティの中、作品が見られる。
そしてアメリカ占領下から日本への返還、ベトナム戦争の終結と、時代の流れに対する人間の生き方が映し出されている。
すごくエネルギーにあふれているし、映画を通して音楽の匂いを感じる。
原作者でもあり、沖縄のロックシーンの中心にいる喜屋武マリーのエンディングの歌もまだ素晴らしい。
知人でもある広田玲央名の独特のだるい感じの演技もうまくはまっている。
この作品に出演している人は、今も活躍している人が多い。
川平慈英や余貴美子さん、大地康雄さんなどの若い頃の芝居が見られるのも面白いし、
あの電車男や海猿の伊藤淳史が子役で出演しているのも楽しく見られる部分だ。
僕の中では崔洋一監督の作品の中でもっとも好きな作品がこれである。
好きな日本のロック映画で5本の指に入る作品だ。
単なるバンドの映画でなく、人間と時代を切り取ったこの作品から、沖縄の背景と音楽の持つパワーを感じてもらいたい。
METAL A HEADBANGER'S JOURNEY(メタル ヘッドバンガーズ・ジャーニー)

監督:サム・ダン、スコット・マクフェイデン、ジェシカ・ジョイ・ワイズ
出演:サム・ダン、アリス・クーパー、トニー・アイオミ、ロブ・ゾンビ、トム・モレロ他
配給:ファントムフィルム/アミューズソフトエンタテインメント
2006年6月24日〜渋谷シネ・アミューズにてロードショー
“ヘヴィ・メタル”の危険な香り
僕が高校の終わりの頃、スタジオ兼楽器屋で、ストラトやレスポールを押さえ、
フライングVなどの変形ギターが幅を利かせ、髪を伸ばし、メロティックサインが日常の挨拶になる奴が出没していた。
リフと呼ばれるループ的で、ディストーションで歪ませたギターの音は、高揚感や危険な香りを与えていた。
あるジャケットには、血みどろの裸の女、そしてあるジャケットには、全面に鋼鉄の仮面。まるでスケバン刑事の様に…。
ステージは過激になり、十字架やゾンビ… “不快”極まりないものもあった。
ジューダス・プリスト、W.A.S.P、スコーピオンズ、マイケス・シェンカーグループ、オジー・オズボーン、
トゥイステッド・シスターズ、クワイエット・ライオット、ゲイリー・ムーア…様々なメタルアーチストのレコードが並び始めた。
パンクとは違う危険なにおい。それは少し宗教的で、ヘッドバンキングをしている人達を見ていると信者にしか見えず、
ライブ会場が集会のように見えた。
そんなヘヴィ・メタルに魅せられた男が、この作品“メタル ヘッドバンガーズ・ジャーニー”の監督をしたサム・ダンである。
彼の想いがビシビシと伝わる作品で、メタルの起源や歴史を追い求め、アメリカ、ヨーロッパをひたすら旅し、アーチストやスタッフに直撃していく。
まるで、子供の頃、夏休みの自由研究で自分の街を調べた時の様に、
ただ純粋に、メタルのルーツを追いかけているのだ。
その追いかけて撮り続けたフィルムを、まるでメタル大事典を作るかの様にまとめている。
“様式美”“社会の闇” 色々な形で表現されたヘヴィ・メタル。
すごく主観的にフィルミングしているものを、すごく客観的に編集し、ドキュメンタリーなのか記録映画なのか分からない気持ちにさせられつつも、
へヴィ・メタルに興味が無い人も見れるように作っているのが、この作品の注目すべき点であろう。
もう1つ注目すべき点は、監督サム・ダン自身がメタルキッズであること。
特にライブの表現は、ミュージシャンのライブDVDを見ている時の様な臨場感にあふれている。
ヘッドバンクしながら、ギター、ベース、そしてマイクスタンドを持ったボーカルの合わせのアクションは、
ひきの画で素晴らしいドリーやクレーンワークを多用し、ギターソロでは、手元のカットが画面いっぱいに広がる。
ライブDVDを作る時の手法、そのままである。
映像で、へヴィ・メタルのライブの魅力を体感しながら、ドキュメントでルーツを見せる。
へヴィ・メタルカルチャーに引き込んでいくパワーのある作品だ。
伊藤政則が人形を使ってメタルを紹介する“PURE ROCK” 今思えば、“sakusaku”の様なものじゃないか?
かつて、“Burn”というへヴィ・メタルの専門誌についていたスコアを見て、
ツイステッド・シスターやクワイエット・ライオットをギターでコピーしていた日々が思い出された。
へヴィ・メタルの危険な香りは永遠に残っていくものであろう。
new york doll(ニューヨーク・ドール)
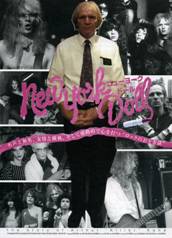
監督:グレッグ・ホワイトリー
出演:アーサー“キラー”ケイン、デヴィッド・ヨハンセン、シルヴェイン・シルヴェイン、スティーヴン・モリッシー(ザ・スミス)、
クリッシー・ハインド(ザ・プリテンダーズ)、イギー・ポップ、
ミック・ジョーンズ(ザ・クラッシュ)、サミー・ヤッファ(ハノイ・ロックス)他
配給:ファントムフィルム
2006年6月3日〜シネセゾン渋谷にてロードショー
“ニューヨーク・ドールズ”と“ニューヨーク・パンク”
AORが西海岸のロック・シーンの中心だった頃、ニューヨークの新しいムーブメントとしてのパンクロックシーンが誕生した。
1973年、ジョニーサンダースを中心に結成されたニューヨーク・ドールズ。
今回の作品の主人公は、そのニューヨーク・ドールズのベーシスト・アーサー“キラー”ケインである。
ニューヨークの伝統的パンクの聖地“CBGB”
トゲトゲしさも何も無い西海岸のロックシーンに飽きたフリーク達が、ドラッグ漬けのパンクアーチスト達を見に集まっていた。
アメリカのストーンズとして銘打ってデビューしたニューヨーク・ドールズも、
ヘロイン漬けでまともな演奏が出来なかったことも多々あったらしい。
ちなみにニューヨーク・ドールズのマネージャーを、セックスピストルズの育ての親、マルコム・マクラーレンがやっていたこともあり、
彼らのスタイルはロンドン、そして世界に広がり、今や伝説のバンドとなっている。
以前、CLUB CITTAにジョニーサンダースが来日した時、そしてジョニーの没後追悼ライブをやった時、
偶然にも僕がカメラを回し、ライブ編集をしている。鳥井賀句氏が仕切って行ったライブだった。
清志郎さんの“COVERS”にも参加しているジョニーが死んだのは、1991年のことであった。
あれから15年。伝説のニューヨーク・パンクムーブメントの雄“ニューヨーク・ドールズ”の名前を久々に聞いた。
あのバンドのベーシスト・アーサー“キラー”ケインは、当時の、アルコール依存症でド派手で危ない印象はまったく消え、
モルモン教徒の優しい図書館のおじいさんとしてフィルムの中にいた。リムジンではなく、バスに乗り、
激しさは消え、おとなしく仕事をしていた。
55歳のあの老人が、本当にアーサーなのか?と思うくらいだった。
ニューヨーク・ドールズが解散したのは1976年。あれから30年が経った。
彼の表情の中に、その30年の歴史が刻まれている。
1つ1つの言葉も、ただのおじいさんが話しているのならたいした言葉では無いものも、
かつてのあの“ニューヨーク・ドールズ”のアーサーとなれば、ここに至るまでどんなことがあったのか想像すらできない部分も多い。
そんなアーサーに再結成の話が持ち上がる。
音楽から離れた男が、かつての自分を取り戻そうとしている瞬間。ベースを質屋から取り戻す時の表情は、ドラマでは描けない
ドキュメンタリーだから味わえる感動を得た。あの表情は、僕の心の中にずっと残ることだろう。そして、再結成へ…。
人生の陽も陰も生きてきたアーサーが伝えたかったこととは何だったのだろうか?
音楽と、音楽の持つ魔力を、30年近く封印した男だからこそ見せられた感動のドキュメンタリー作品である。
パンク・ロックは音楽という枠に納まるものではない。
パンク・ロックとは、スタイルに納まることができない、破壊的かつ強烈な生き方のことである。
CROSS CHORD

監督:井上秀憲
出演:森久保祥太郎、高橋広樹、IKURA、高山猛久、エレキコミック、杉本彩 他
配給:Broad Marks inc
2006年7月22日〜RelaX AOYAMAにてロードショー
“BANDとは絆”
自分の作品を解説するとは何と難しいことなんだ。何度もフライヤーを見ては2,3行書き、止まってしまう。
言いたいことは作品に詰めたつもりだし、なかなか客観的に見れないものである。
今回の作品は、バンドにおける“絆”というものを描きたかった。誰もが自分の欠点を知っている。
でも、そこを隠そうとする。家族のように身内だと自分の弱さを見せられるかもしれないが、
なかなか他人には見せられないものだと思う。バンドは家族のようなものであると僕は思っている。
色々なことを共に超えていくことで、本当のバンドになっていくものである。
特に今回は、主人公の4人が、実生活でもバンドのように絆ができたことがうれしい。
自分たちで勝手にバンドリハーサルをしてみたり、撮影後も編集をメンバーで集まって見に来たりと、
本当のバンドよりバンドっぽい時もいっぱいあった。人間は30近くになると変われるようでなかなか変われない。
だからこそ、今まで自分の生きてきた道を受け止め、次につなげなくてはならないと思う。
そして、自分が共に生きる仲間に何らしかの影響を与えていることも忘れてはいけない気がする。
そして、自分の周りの人間の影響によって自分自身が日々変化していることにも気づかなくてはいけない。
今回は少し説教臭いことを言っているが、自分の作品の解説を書くと照れるので、この作品を作った気持ちを書いてみた。
IKURA氏が出演していることにも注目。
僕の中でオーナーは父親的威厳と先輩的優しさと、男としての魅力を持つ人物像に描きたかった。
IKURA氏の演技は決してうまいとは言えない。しかし、味がある。
BANDMANとして生きた男の持つ味があふれている。
現在レンタル中なので、是非一度見てもらいたい。
何度も言うようだが、BANDとは、音で結ばれた絆の結晶である。
ポリス インサイド・アウト

監督・脚本・プロデューサー:スチュアート・コープランド
出演:スティング、アンディ・サマーズ、スチュアート・コープランド 他
配給:スタイル・ジャム
2007年3月31日〜TOHOシネマズ六本木ヒルズにてレイトショー
“本人の目から見たロックスター誕生ドキュメント”
70年代後半から80年代初めまで、一気に世界的スターになり、そして消えた“THE POLICE”
スティングを知っている人は僕らの世代では多いだろうし、ドラムでもあり今回の作品の撮影・監督をしたスチュアートは、
オリバー・ストーンやコッポラの映画音楽でも有名だ。日本にも二度来日し、84年活動を休止する。
この作品は、ドラムのスチュアートが“スーパー8”というフィルムカメラが少し売れ始めた時、買ったところから始まる。
いわゆる8mmフィルムカメラである。8mmフィルムカメラには、“スーパー8”と“シングル8”というカセット式のものがあり、
今みたいにDVカメラやHi8が出てくるまでは、すべてこれであった。スーパー8はポジフィルムであり、
確かノーマルのコマ数だと4分くらいしか撮影できなかったと思う。
そんなカメラを移動・ホテル・打ち合わせ・ライブ・レコーディング、もちろんプライベートまで回しまくっている。
構図が甘いところはあるものの、ステージから見た客の画や、出待ちのファン、車の中から見た目線、
つまりアーティストと同じ目線、“THE POLICE”と同じ目線の画が続いていく。
さらには、メンバーの素の部分やスタッフの素の表情が出ていて、見ている側がスチュアートと同じ目線、
つまり、自分がどんどんロックスターになっていく気分を味わえる作りになっている。
僕も高見沢俊彦や忌野清志郎というロックスターのドキュメンタリーを撮ってきた。
本人に構えさせないため、最少クルーで動く。
でも、そんな被写体の近さとは訳が違う、鏡にカメラを回している自分が映りこんでもOKだし、声を出してもOK。
すごくうらやましい。そうなればいいのに…と思う時も多々ある。
特に面白いのが、ライブ中、ドラムの後ろにカメラを固定し、解説しながらスチュアートがライブをしているところ。
これは彼にしかできない。何故なら、彼自身が“THE POLICE”だから。
まさに、ロックスターが誕生していく過程を内側から見せた超貴重映像でつづるドキュメンタリーフィルムである。
ROUGH CUT&READY DUBBED

監督:ハーサン・シャー、ダム・ショウ
出演:スティッフ・リトル・フィンガーズ、コックニー・リジェクツ、パープル・ハーツ、セレクター、シャム69、
パトリック・フィツジェラルド、ア・サーティン・レイシオ、ジョニー・G、UKサブス、ジョン・ピール
配給:ナウオンメディア
2007年1月20日〜シアターN渋谷にてロードショー
“UK PUNK NEVER DIE!!”
1978年マルコムマクラーレンが結成させたあのパンクグループ“セックスピストルズ”が解散した。
Vo.ジョニー・ロットンとG.スティーヴ・ジョーンズ、Dr.ポール・クックそしてBのシド・ヴィシャス。
特にジョニー・ロットンとシド・ヴィシャスは世界的なスーパースターであろう。
ジョニー・ロットンは後にパブリックイメージLTDを結成。
そして、シド・ヴィシャスは恋人のナンシー・スパンゲンをピストル射殺。
翌79年、ヘロイン多量注入でニューヨークで死亡。本当に破天荒な人生である。
ステージにヌードの女性をあげ、演奏中止。楽器、マイク、アンプを壊し、フェスまで出場禁止。
メーカーからは契約破棄。放送禁止。テムズ川でボートの上で演奏し、マルコムら10人が逮捕…と
彼らのエピソードはいくつ書いても書ききれない。
国に対しての不満、商業主義への反抗、そしてピストルズが社会に対して切り開いてきたパンクという音楽とそれが持つ力の大きさ。
若者達はパンクという音楽とそれが持つ力に興味を抱き続けた。
ピストルズ解散後、UKパンクシーンを引っ張っていったアーチスト達とそのシーンを描いたのが、
この“ROUGH CUT&READY DUBBED”である。
スティッフ・リトル・フィンガーズ、パープル・ハーツ、セレクター、シャム69などUKパンクシーンの中心的バンドが続々と出てくる。
なんと、この作品、1982年に出来たものであり、日本に上陸して公開されるまで25年もかかっている。
当時のものだけあって、音も少し悪いし、画も少し汚い。しかし、それがより、25年前のリアリティさを感じさせてくれる。
ストレートで荒々しいその姿は、当時のパンク魂を感じさせてくれる。
破壊的な勢いで進んでいくアーティストとオーディエンス。
ファンの声も多く入っているこの作品は、単なる発信側から捉えているわけではなく、シーン全体が見えてくる。
反発するイギリスの若者達。今、静かになった日本の若者達には見えないパワーがぎっしり詰まった作品である。UKPUNK NEVER DIE!!
バンドワゴン

監督:リー・ホームズ 出演:ジョン・シュルツ 他
1996年 アメリカ映画
“バンドツアーの真髄”
かつて僕は“CROSS CHORD”というバンド映画を撮った。そのテーマに近いのが、まさにこの“バンドワゴン”である。
バンドとは絆である。個性的で弱みを持っている4人が、ひょんなことからバンドを組み、絆を深めていく。
お互いに自分のだめなところや自己顕示欲をもろに出しながら、時には引きこもりながらも、相手の良い所も悪い所も受け入れていく。
音楽という1つのキーワードがつないで“ファミリー”より強い何かを作っていく。
この作品でのマネージャー役的存在が、僕の作品ではライブハウスのオーナーのIKURA氏だ。
第三者が入って導いて守ってあげるのも、また素晴らしい。多くを語らないが、裏でしっかり守ってあげる。
この“バンドワゴン”と“CROSS CHORD”をセットで観てもらうと、バンドの真髄が分かってもらえるだろう。
誰もが完璧な人間ではない。未完成の人間だからこそ、バンドは人間を成長させてくれる。
そして、自分達が信じていることを貫くことが大事である。
“ロック人生はつらい”という台詞があるが、何でも貫いて生きていくことはつらい。
でも、そこを乗り越えた先では、数倍楽しい何かを得ることができる。
初めのシーンでTakamineのアコギのヘッドのアップから始まるのも、音楽的でちょっとマニアックでワクワクする。
その後、gibsonのレスポールとかに変わっていくところにも、バンドに賭ける彼らの気持ちがうかがえる。
貧乏なのに音楽に全ての金を注ぎ込んでいる感じが気持ちよい。
4トラのカセットで録音しているのも、地味な感じで好感が持てる。ちょっと残念なのが、無意味に揃っているヘッドバンキング。
やらせている感じが少し伝わってきた。それ以外のライブシーンは気持ちよかったのに…。
トラブルを抱えながら、1台のシボレーのバンで旅をして、友情を深めていく彼らの姿は、プロのバンドよりバンドらしかった。
変に新幹線や飛行機で移動しているバンドのメンバーよ、この作品を見て、自分達のバンドを見つめ直しなさい。
スティル・クレイジー

監督:ブライアン・ギブソン
出演:スティーブン・レイ、ビル・ナイ、ジミー・ネイル、ティモシー・スポール、ブルース・ロビンソン 他
1998年 アメリカ映画
“大人のロック魂とロックンロール”
この作品“スティル・クレイジー”は、20年前に解散したバンドがおじさんになって復活していく様を描いた
“おっさん版バンドワゴン”である。
大きな野外のロックフェスに出演した若い頃の栄光。
そして、20年後、ただの瓦拭きになっていたり、家賃を滞納しながら農園で働いていたり、
過去の栄光で手に入れた家も売却しなくてはならない状態だったりと、皆転落していった。
そんな中、再結成するバンド“ストレンジ・フルーツ”。
再結成したもののギタリストは死亡説が流れ、若いギタリストを入れる。
当時の女マネージャーも奮闘し、バス1台でヨーロッパツアーを回っていく。
ライブハウスでは違うジャンルの音楽が台頭し、時代は明らかに変わっていた。
ふざけてばかりのオヤジ達も音楽のことだけは本気なところも、ロックオヤジらしいリアリティがあって面白い。
この手のツアートリップもののきもは、マネージャーの存在無しには語れない。
そして、今回は、死亡説の流れたギタリスト。実は精神病だったのである。
20年ぶりに同じロックフェスに出る為、マネージャーが見つけてきて出演させようとするのだが、マスコミのキツイ口撃で病が再発しそうになる。
この映画の見どころは“バンドが固まる瞬間”である。
ライブを見に行くと、今までバンドとしての一体感がまったく見られなかったグループが、突然凄い一体感を見せる時がある。
そして、一度固まったバンドは、その後、そのパワーを持続していくことが多々ある。
バンドはグループを組んだ時にバンドになるのではなく、ライブや音楽を通じ、一体感が出来た時に初めてバンドになるのだと僕は思っている。
そんなバンド臭さがプンプンにおってきそうな“スティル・クレイジー” 大人だから出せるロックンロールとバンド観。
E.L.O.のジェフ・リンがサントラに参加しているのも聴きどころだし、ジミヘンの歯を持っているなど、
ロックファンなら思わず笑ってしまう部分もたっぷりある。ロックファン必見の1本である。
ロニー 〜MODSとROCKが恋した男〜

監督:ルパート・ウィリアムズ&ジェームズ・マッキー
出演:ロニー・レイン、エリック・クラプトン、ピート・タウンゼント 他
配給:ハピネット
2007年5月12日〜シアターN渋谷他にてレイトショー
“栄光と挫折の中で”
ロニー・レイン。あのロッド・スチュアートやロン・ウッドも在籍していた“フェイセズ”を作った男。
60年代のイギリスのMODSやROCKのシーンの中で、特異な存在として輝き続け、1997年に死去。
この作品“THE PASSING SHOW”(邦題:ロニー〜MODSとROCKが恋した男)は、
そんなロニー・レインのドキュメント映画である。
過去のライブやTVの映像、生きていたときのインタビュー、友人達が語るロニー、そして数々の写真。
とにかく子供の頃の写真が多い。ロンドンのイーストエンドに生まれ、母は多発性硬化症で動けず、父は運転手という貧しい家庭。
父親はロニーを溺愛し、楽器を勧めた。ロニーの小遣いはウクレレをパーキングで弾いて大人達からもらうことだった。
バンドを結成し、“スモール・フェイセズ”と名づける。後のフェイセズである。
この頃、ストーンズやthe WHOなどがどんどん売れていくが、スモール・フェイセズはなかなか芽が出なかった。
しかし、作品の能力は高く、やっと1人のプロデューサーの目に留まる。彼の名はグリン・ジョーンズ。
ストーンズ、ビートルズ、レッド・ツェッペリン、クラッシュなどを手がける大物のプロデューサー。彼の後押しで遂にデビュー。
ここから一気にスターの道を歩みだす。
ロックをオペラとしてアルバムを作ってみたり、リフ中心になり始めている頃にカントリーやブルース色を足したりと
他のグループとはまったく違うことをやってみせた。
メンバーが脱退し、ロン・ウッドとロッド・スチュアートを加入させ、“フェイセズ”に改名。
全米ツアーを周ったり、25万人の野外ライブイベントなど、本当にNO.1ロックバンドになる。
しかし、ロックスターになりきれないロニーは脱退。スリムチャンスというバンドを組み、ソロで作品色だけを追いかけるようになる。
クラプトンやピート・タウンゼントとコラボレーションしたり、サーカス団のテントトレーラーでヨーロッパの田舎を周る
“PASSING SHOW”というツアーを周ったり…
このツアーが、オープニングのボンネットバスがイギリスの田園地帯を走っている風景とクロスオーバーさせられる。
しかし、73年、母と同じ多発性硬化症になり、ピックも持てなくなる。もちろんベースも弾けない。
彼はチャリティをすることを決める。
クラプトン、ジェフ・ベック、チャーリー・ワッツ、ジミー・ペイジ、ビル・ワイマン。ロニーの音楽を愛する気持ちが彼らを集めた。
1997年、彼はコロラドで静かに息を引き取る。栄光と挫折の中で音楽だけに生きた男、ロニー・レイン。
彼の音楽は今も生きている。
スクール・オブ・ロック

監督:リチャード・リンクレイター
出演:ジャック・ブラック、ジョーン・キューザック、マイク・ホワイト、サラ・シルヴァーマン 他
2003年 アメリカ映画
“ただの子供映画では無い本質を描いたロック映画”
ジャック・ブラックを世界的有名にした“スクール・オブ・ロック”
ロックを愛し、社会になじめない男が、友人の代理教師の依頼を嘘をついて自分で受け、
そのクラスの生徒達とバンドを組んで、ロックフェスティバルに出場するという、いたってシンプルなロックコメディ映画である。
まず、子供達がしっかりと演奏していることで、ロック映画としてのドライブ感がしっかり感じられる。
子供達は1万人を超えるオーディションから選ばれたスーパープレイヤー達。
クランクイン前は、バンド練習ばかりだったと言われているが、まさに、バンドとして成立している。
さらに、ロック的な面白さがいっぱい詰まっている。
たとえば、シェビーバンをバンドのツアーバンの様に改造して学校に行ったり、ツェッペリンの歌でシャウトしたり、
黒板にはロックの歴史が書いてあったり、笑いのポイントが、まるでミュージシャンの会話に出てくるような話題ばかりである。
AC/DCが愛用していたSGを弾く時は、AC/DCの様に短パンをはいていたり、ダイブで受け止めてもらえずフロアに落ちたりと、
ロック的笑い所が随所に描かれている。
そして、この映画の見どころは、何と言っても、ジャック・ブラックの存在感だ!
いつもハイテンションで笑いを作り続けるパワー。アメリカンスタイルの“ザ・コメディアン”という感じだ。
彼自身も役者でありながら、ミュージシャンであるという経歴を持っているので、音楽の部分にまったく手を抜いていない。
実際にギターを演奏し、ライブで実際に客をあおっていく。
最近日本でいくつかバンド映画があったが、あてぶりで押さえているポジションも違うのを見てしまうと、一気に冷めてしまう。
しかも、役者がミュージシャン独特のノリを出せない人が多い。
でも、この“スクール・オブ・ロック”では一切そんなところが無い。ジャックはまさにミュージシャンそのものを演じている。
パワーとエネルギーの塊のロック映画。子供達に成長させられていく大人のロッカー。
心温まり、そして笑えるエンターテイメントロックムービー“スクール・オブ・ロック”僕のお気に入りのロック映画の1本である。
ドアーズ
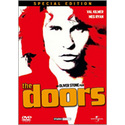
監督:オリヴァー・ストーン
出演:ヴァル・キルマー、フランク・ホエーリー、ケヴィン・デロン、メグ・ライアン 他
1991年 アメリカ映画
“狂宴の男の生き様”
巨匠オリヴァー・ストーンが、伝説のバンド“DOORS”を映画化した作品。
ジム・モリソンを軸に作られた作品だが、アメリカのライブハウスの感じとか、LIVEそのものの感じをすごくリアルに表現している。
L.A.の“Whisky a gogo”のLIVEシーンがあるのだが、以前僕もここでLIVE撮影をしたことがあって、
あの時体感したことが手に取るように伝わってきた。
ステージを作りこんだ作品はいっぱいあるが、この作品は客やスタッフの雰囲気まで作りこんでいる。
全体的には、シルエットの使い方が印象的だった。
夜の都会L.A.の早送りと合成の紫の月とか、ガラスの窓に雨が撃ちつけられている中でのシルエットのベッドシーンとか、
重い感情を象徴するカットが、作品に僕を引き込んでくれた。
ジム・モリソンに対して僕が持っているイメージは、狂乱と詩的な部分。
その原因が子供の頃に見たインディアンの悲劇だったということを、この映画では軸にしていくが、
そんな一瞬の出来事が1人の人間に大きな影響を与え、多くの人に影響を与えるバンドにしてしまったこと。
ある意味、アーチストに宿る宿命みたいなことを考えさせられる作品であった。
とにかく、役者達が本当のバンドに見えた。
ジム・モリソンを演じるヴァル・キルマーの表情やアクションを見ているといかに研究したのかが、すごく伝わってくる。
ちょい役だが、アンディ・ウォーホールを演じていた役者は、そっくりすぎて一瞬本人じゃない?と思うほどであった。
UCLAの映画学科に少しだけいたジム・モリソンを表現する中、当時のベニスビーチの感じなどもリアルに表現していて、
オープニングからとても入りやすく引き込まれた。
当時のサーファー、スケーター、水着、ビーチサイクル。時代的にも音楽的にもすっと入り込めるリアリティを感じさせるバンド映画。
ジム・モリソンという1人の詩的な狂人の真の姿を見ることで、精神世界を見せる生き方の大変さを感じさせてくれる。
狂宴的音楽生活の中で、彼が見たものは何だったのだろうか?
